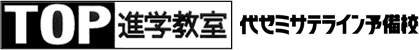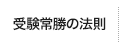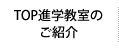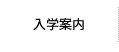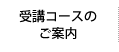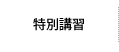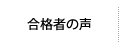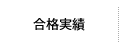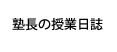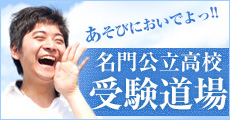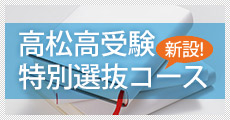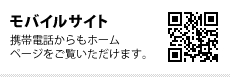【新中1英数入門講座】
2026年02月27日
★ 「新中1 英数入門講座」 英語数学の理解状況に応じて指導します。個別指導です。
・ 内容 英語:be動詞、一般動詞の文 数学:正負の数
・ 日程 3月17日(火)・18日(水)・19日(木)・23日(月)・26日(木)・31日(火) ⇒ 14:00~19:15 より90分間選択
3月9日(月)・10日(火)・16日(月)・24日(火)・27日(金)・30日(月)・4月1日(水)・2日(木) ⇒ 16:30~19:15 より90分間選択
以上より3日間選択(時間帯の組み合わせ自由)
・ 受講料 6,600円
・ 申し込み方法 こちらから
・ その他 募集は数名です。
【2026 中3特別選抜コース】
2026年02月26日
2026年度授業のコース紹介です。
今日は、【中3 特別選抜コース】詳細はこちら
このコースは、高松高校・高松一高・三木(文理)上位合格を目指すコースです。入試・診断テスト対策のコースです。一斉授業がメインです。一斉授業ですが、特別な解法が必要な問題、頻出問題の解法の解説になります。自力で解けるような問題を授業で取りあげることはありません。要点を絞った授業内容です。したがって、ある程度の学力は必要なため、「選抜制」です。
中2の「学年末テスト」「診断テスト」の順位・得点により、受講を許可します。また、それらの成績が思うように取れていない場合には、「選抜テスト」での合否判定も行います。
指導教科は、英数国理社の5教科必修です。
2026年3月21日(土)開講です。事前の面談、成績判定が必要なため、受講ご希望の場合には、お早めにご連絡お願い致します。
* 例年、TOP進学教室在籍の中3生のほとんどが受講し、高松高校、高松一高、三木高校(文理)等の合格を勝ち取っています。
【2026 高松高・高松一高・三木(文理)進学コース】
2026年02月25日
2026年度授業のコース紹介です。
今日は【高松高校・高松一高・三木(文理)進学コース】 詳細はこちら
このコースは、高松高校・高松一高・三木(文理)上位合格を目指すコースです。「定期テスト」でトップを目指します。学校進度に合わせて予習を進めます。テスト前には、テスト範囲の演習を繰り返します。一斉授業ではなく、「個別演習型指導」です。各自のレベルに合わせて問題演習を重ねることによって、トップを目指す実力を養成します。
教科は、英数国理社から選択して受講できます。1教科から可能ですので、得意科目伸長にも適しています。曜日も月~木・土から選択できます。
一斉授業ではありませんので、どの中学校の生徒でも受講できます。
トップを目指す意欲ある生徒の受講をお待ちしています。
お問い合わせ、面談のご希望などは、こちらから
高校生の3月は時間がある
2026年02月24日
三木高校は、先週で学年末考査が終わりました。高松一高は今日終わります。高松高校も来週前半で終わります。
3月は、テストもないし、休日も多いのです(公立高校入試の日は休日ですし、20日からは春休みのはず)。4月の第1週も春休み。つまり、1か月ちょっと時間が十分にあります。例年の夏休みくらいの期間ですね。
ここで、差を一気に広げるチャンスです。
高校の授業もあまり進みませんから、思う存分に自分の勉強ができます。高校の宿題なんて、さっさと片づけて、自分の得意教科を伸ばし、不得意教科を克服する勉強の期間にすべきでしょう。
高校生の塾生には、「受験戦略面談」を行い、この期間に取り組むべき学習の指示をしています。
仕上がってきた
2026年02月23日
中3生の「個別演習型指導」では、時間を決めて「入試予想問題演習」をやっています。
ちょっと難しめの問題も入っていて、制限時間内に解くにはコツが必要な予想問題。
冬期講習から練習を重ねてきたので、ミスも減ってきました。また、記述問題も中身がしっかり書けるようになってきています。
何回も塾生には伝えていますが、取れる問題は確実に得点する、これに尽きるのです。公立高校入試は、同じレベルの受験生が集まります。同じ得点に何人も、いや場合によっては何十人も並びます。
例年同様、仕上がってきてはいますが、油断禁物。さらに、磨きをかける、残り2週間。
間違えることによって覚えることも多い
2026年02月22日
日々の学習の過程で間違えることは、良くないことではありません。
いや、むしろ、間違えることで、その時点での理解できていないところ、覚えていないところが、明らかになります。
そして、それを理解できるように、覚えるように勉強する、それが向上への近道です。
ですから、日々の問題演習、宿題等で、間違えること自体はあまり問題視していません。最初から100%完璧な人はいないはずですし。
大事なのは、その先。分かってる問題、分かってない問題を区分けしたら、分かってない問題を徹底的に、分かるように、解けるように復習する。そのことは、事あるごとに指示をしています。
「個別演習型指導」は、こんな高校生に向いています
2026年02月21日
昨日に引き続き、高校生版です。
・ 国公立大学、難関私大を目指している
・ 自分のペースで勉強したい
・ 分からないところを中心に指導してほしい
・ 問題演習を行うことによって、得点力を上げたい
・ 学校のペースに合わせるのではなく、どんどん先取りしたい
などなど。
一斉指導ではないので、受講生がとりくんでいることは皆それぞれ違います。個々のやるべきこと、やりたいことを聞いて、その日の学習内容を個々に指示しています。
高松高校や高松一高など、通学に時間がかかる場合には、課題を出し過ぎると、オーバーワークになってしまうので、部活の忙しさ加減に応じて、個々に学習内容を変えています。また、高校の教材メインで学習している塾生もいます。
また、特に高校1年生の場合には、中学と高校の勉強のギャップ(レベル、量)を日々の指導の中で伝えるようにし、高校1年生段階から、日々の家庭学習の重要性を強調して指示しています。
お問い合わせ、また、無料体験授業のお申し込みは、こちらから
「個別演習型指導」は、こんな中学生に向いています
2026年02月20日
TOP進学教室が取り入れている「個別演習型指導」は、一斉指導でもなく、かといって、1:2のような個別指導でもありませんが、私がすべての生徒の学習理解度、進度を把握して、学習内容を指示しています。
「個別演習型指導」が向いているのは、
・ 一斉指導ではなく、もっとどんどん先に進みたい。
・ 理解できるところは自分でやって、分からないところのみを教えて欲しい。
・ 問題演習をすることで、得点力を上げたい。
・ 周りを気にすることなく、自分のペースでどんどん進めたい。
・ 定期テスト向けの勉強は自分でできるので、診断テストや入試向けのレベルの高い勉強がしたい。
・ 高松高校、高松一高を目指し、将来は国公立大学、難関私大に進学したい。
・ 静かな環境で、集中して勉強したい。
と思っている中学生です。
無料体験授業をご希望の方は、こちらから
受講に関する面談は、日曜日も開催しています
2026年02月19日
受講に関する面談は、以下の日曜日も開催中です。
2月22日(日) 13:30~17:00
3月1日(日) 13:30 ~17:00
3月8日(日) 13:30~17:00
平日は、13:30~16:00 に開催中です。
面談は事前予約制です。
ご予約は、こちらから
2026年度版に更新しました
2026年02月18日
このHP掲載の内容を、2026年度版に更新しました。
授業内容、料金等一部変更しております。
詳しい案内パンフレットの請求は、こちらから