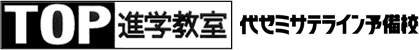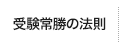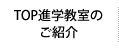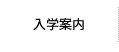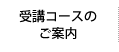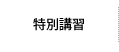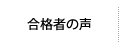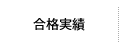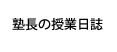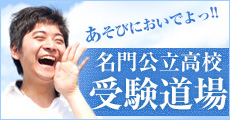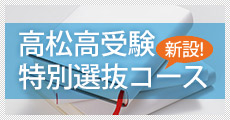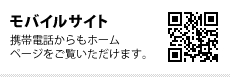【満席】「国語読解解法の奥義」
2024年07月10日
夏期講習の「国語読解解法の奥義」は、満席となっております。
キャンセル待ちは承ります。
また、ご要望が多数あれば、冬期講習でも開講する場合がありますので、受講ご検討の方は、ご連絡おねがいします。開講した際には、優先的に先行申し込みできます。ご連絡はこちらから
「中3夏期講習」事前課題指示完了
2024年07月09日
「中3夏期講習」は、7月20日スタートです。6月末から事前課題の指示を個別に行っていましたが、本日完了しました。
「夏期講習」では、授業時にテストがありますが、毎回の出題範囲を伝え、事前に取り組むべき課題を指示しています。夏休みになってから、「さあやるぞ!」とスタートするのではなく、今から早めにスタートです。
夏休みに入るまで、10日あります。早く始めた方が余裕を持って取り組めます。
中3生を含めて「夏期講習」ご検討の方は、お早めにお問い合わせ、お申し込みお願い致します。満席の学年、コース、曜日、時間帯があります。
お問い合わせは、こちらから
【夏休みの成功計画②】 勉強する環境
2024年07月08日
今日は、「勉強する環境」についてです。
最も大事なのは、「集中して取り組める環境」です。
静かである、スマホやゲームなどの誘惑がない、適度な室温・・・など、でしょうか。
自宅で取り組めるのが理想ですが、学校や塾の自習室、図書館など、自宅外の場所での学習も、考えてもいいでしょう。
自宅で1日中こもってずっと勉強するのが苦手な場合には、気分転換も兼ねて、午前中は学校、午後は塾、夜は自宅、などど場所を変えて勉強するのも効果があります。
スマホから逃れるためにも、ある程度周囲の監視のある場所で勉強するのです。
個々に集中できる環境は異なるとは思いますが、よりよい環境の下、取り組むとよいでしょう。
【夏休みの成功計画①】 起床時刻
2024年07月06日
夏休みが近づいてきました。有意義に過ごすためのポイントを書きます。
まずは、「起床時刻」について。
ズバリ、
「普段学校に行くときと同じ時刻に起きる」
これに尽きます。
いつもと同じ時刻に起きれば、午前中に3時間程度の学習時間は確保できますし、これまでと同じ生活リズムですから、規則正しい生活が送れます。
受験生の場合には、午前中に少なくとも3時間の学習時間を確保するのが重要。午後に3時間、夜に3時間勉強しても、まだ、休憩時間等は十分に取れます。無理がありません。
もちろん、比較的涼しい早朝の時間を活用するために、いつもよりも早く起きるのは構いません。ただし、その場合には、夜も早く寝て、睡眠時間が短くならないようにしましょう。
起床時刻が遅くなって、勉強開始が午後になると、すべてが後ろにずれていきます。就寝時刻も遅くなり、ますます起床時刻も遅くなって、生活リズムが崩れます。夏休み中は、やはり、午前中から活動するようにしたほうがいいです。
次回は、「勉強する環境」について記します。
途中式は重要
2024年07月05日
小学生、中学生の算数、数学を教えるときには、必ず途中式を書き、残しておくように指導しています。問題集やプリントによっては、書き残しておくスペースがない場合もありますが、その場合には、他の紙などに書いて、その場に貼っておくように指示しています。
途中式がなぜ必要かというと、間違ったときに、どこでどうして間違ったのかを知ることができるからです。例えば、約分で間違ったならば、
「自分は約分でミスしやすいから、約分の時には気をつけてやろう」
という意識づけができます。
それが、途中式がない(あるいは消してしまった)場合には、間違ったときにその原因が分からないままです。それに、直す場合には、また最初から計算しなおす必要があります。時間の無駄ですね。
でも、別の理由もあります。
それは、高校の数学では、途中式がないと〇にならない、からです。
答に至る過程が必要なのが、高校の数学です。
どっちかというと、過程の方が重要で、計算ミスで最終的な答が間違っていても、合っているところまでは、部分点をくれることが多いです。(小中の算数、数学では、まず部分点はありません)
後々のことを考えて、小中の段階から、途中式を書いて残しておくことについては、その都度指導しています。小中高と一貫して、私が直接指導しているからこそ、そうした指導ができます。
差がつくのは、ほんのちょっとしたことから
2024年07月04日
小学校、中学校、高校では、クラス全員同じ授業を受けています。ですが、成績の差はできます。
「塾に通ってるから」という理由もありがちですが、それも違います。同じ塾に通っても成績の差はあるのですから。
では、どうして差がつくか?
私は、授業を受けた後の復習や、予習、宿題の取り組み方にあると思っています。授業を受けっぱなしにしてる子、予習、復習をきっちりやって自力でできるまで取り組んでいる子、分からないところは質問して解決している子、・・・。多分、そういうところの差です。それが、長い年月積もり積もって、大きな差に。
成績を向上させようと思ったら、予習や復習に自ら取り組む意欲、「自学力」は必要でしょう。なんでもかんでも教えてもらうことになれてしまうと、自分で考える力は弱くなります。そして、自分で考える力が弱くなったから、困らないようにさらに手を差しのべすぎると、ますます弱くなっていきます。困らないように困らないようにと、助けているのが、逆効果になっていることもあるのです。
周りに合わす必要はない
2024年07月03日
「友達はまだ本格的に勉強してないから」
と、周りに合わす必要はありません。受験勉強は、早くやったもん勝ちです。ゴール(入試日)は、決まっています。ならば、早く始めた方がいいのです。
ちなみに言っておきますが、大都市圏の私立中高一貫校は、高校の学習内容は、高校2年までで終えます。高校3年生の1年間は、受験のための学習です。中学の内容は、中学2年までで終えます。中3の時には、高1の内容を学習します。高1の時には、高2の内容を学習するのです。
つまり、彼らは1年早いのです。彼らと受験で競うわけですから、自分の周りと比べてはいけません。高1になった段階で、すでに1年遅れているのが現状です。
中1の1学期の成績は暫定的
2024年07月02日
期末テストの成績が返ってきているようです。
中1生は、前回の「中間テスト」と比較して、どうだったでしょうか? 「中間テスト」よりは出題範囲も広くなり、多少は問題も難しくなっているはずです。
良かった、良くなかった、いずれにせよ、今回の1学期の成績は暫定的です。
1学期は、入学して、部活も始まり、GWもあり、その後、中間テスト、運動会、宿泊学習(三木中)、そして、期末テスト、と次々に行事があり、時間をかけて勉強できなかったという人もいるはずです。また、部活も始まって、疲れて、勉強が後回しになったという場合もあるかもしれません。
また、これから行われる定期テストと比較すると、テスト範囲は非常に狭かったです。
ということもあって、本当の実力差が出るのは、2学期です。これは、毎年実感しています。
これから夏休みに入ります。そして、2か月間半は、学校のテストがありません。この期間の過ごし方で、成績はどのようにも変わります。1学期の成績が良かったからといって安心できないし、良くなかった場合でも、十分に挽回可能です。
とはいえ、中学校生活初めての夏休み。43日間どう過ごせば、2学期以降伸ばすことができるのか、分からない、また不安な場合もあると思います。個々のテスト結果に応じて、夏休み中に取り組むべき勉強内容、方法のご提案を行っています。
昨日も書きましたが、次に向けての行動は早い方がいいでしょう。
こちらもご覧ください。
今日から、今年の後半戦
2024年07月01日
今日から7月。
あっという間に今年も半分終わりました。
今年の正月に、「今年は受験生になるから頑張るぞ!」と誓った受験生も多いと思いますが、すでにその半分は終わったわけです。誓い通りにやれたでしょうか?
上手くやってこれた人は、受験までの残り期間もこの調子で。
そうでなかった人は、受験までの残り期間は、相当時間をかけてやらないといけないでしょう。周りの人がやってる時間以上に、取り組む必要があります(もちろん、時間だけかければいい訳ではありませんが)。
いつから再スタートをきるかというと、今日、今からです。明日からではないです。明日から、と決めた段階で、すでに先送りしていますよね。反省しているなら、今すぐです。
何から手を付ければいいかは、個々のこれまでの成績や志望高校、大学によって異なります。「友達がやってるから、私もそれをやろう」というのは、よくある間違った取り組み方です。成績や志望校や得意苦手科目が違うはずです。自分で判断できないなら、学校の先生なり、塾の先生なりに尋ねてみるといいですね。客観的に判断できるはずですので。
解けて当たり前のことを確実に正解する
2024年06月29日
高得点を維持するには、応用問題を解けるようにすることも重要ですが、もっと重要なのは、
「解けて当たり前の問題を、100%確実に正解する」
ということです。
高校入試で、高松高校や高松一高を目指す場合には、他の受験生も各教科40点以上は取ってくるわけですから、ミスは致命傷になりかねません。誰もが解ける問題を、自分だけミスすれば、確実に差が開きます。授業中によく言いますが、誰もが解ける問題を確実に正解すれば、負けることはない、と。
解けて当たり前の問題を確実に正解することは、絶対に必要です。
そういう問題をミスするのは、やはり油断だと思います。解けて当たり前レベルだから、解く際にも注意力が散漫になりがちですし、見直しも十分にできていない可能性があります。易しい問題こそ、手を抜かずに解くべきです。