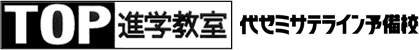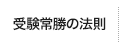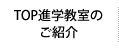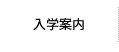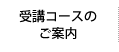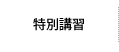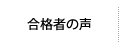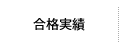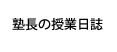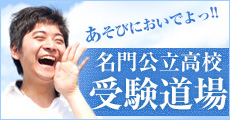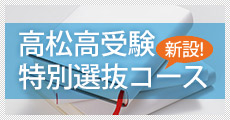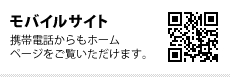勉強する過程での間違いはOK
2025年02月15日
テストとか入試ではダメですが、日々の勉強を進める中で、「間違う」ことは全く問題ありません。いや、むしろ「間違う」ことによって、理解が深まることもあります。
「あぁ、正しいのはこっちだったか」と。
日々の勉強の中で、問題を解いて間違ったら、それを正しい方向に修正する、それが、本当の勉強というものです。
中には、間違うことを恥ずかしいと思ったり、悪いことだと思ったりしている場合もあるでしょう。
間違ったところを消しゴムで消して、解答を見て、正しい答えを書いて、あたかも最初から正解していたふりをする、これは一番成績が上がらない例です。間違ってもそれを次の勉強につなげていけばいいのです。
間違うことは、恥ずかしいことでも、悪いことでもありません。
第1志望を受ける
2025年02月14日
私は、基本的には、第一志望は受験すべき、と思います。
極端に合格レベルとかけ離れている場合は別ですが、可能性があるなら受験すべきです。これまで第一志望を目指して勉強してきたわけですから。合格すればそれでもちろんよし、仮に不合格でも、周りのライバルに勝てなかった、という事実はあるのですから、納得できると思うのです。一番良くないのは、「あの時受けておけばよかった・・・」と後悔すること。こればかりはどうにもなりません。受けておけば、そうしたことは起こりません。入試は受験者全員が100%合格するわけではありませんから、滑り止めなりそうした準備はもちろん必要ですが、そうした準備をしたうえで、第一志望は受験すべきでしょう。
私の進路指導方針はそういう考えなので、第一志望の受験をやめて、合格できそうなところを安易にすすめることは、まずありません。
「これは自信ある」という参考書、問題集をつくる
2025年02月13日
大学受験の場合、どの教科も、「これはやりきった」「これは自信ある」という参考書、問題集を各教科1冊ずつ作るべきです。基礎力も定着していないのに、あれもこれもやるのは時間の無駄だし、力はつかないでしょう。
高校生の質問に答えているとき、「これ4STEPに同じような問題が載ってる」とか、「構文150に載ってる例文とほぼ同じ」と、塾生に指摘することがあります。そのくらい典型的な問題でも定着していないこともそれなりにあるのです。つまり、教科書で習った高1、高2時点での理解があやふやですし、「4STEP」とか、「構文150」の内容が定着していないのです。だから、そういう場合には、再度その参考書、問題集に戻って、確認するように伝えています。
大学受験であっても、最終的には、参考書や問題集に載っている内容を使って解くことになるので、高1、高2時の基礎力は何よりも大切です!
今日は「診断テスト」、明日から三木高は期末考査
2025年02月12日
今日は、中学生の「診断テスト」でした。
出来具合も気になるところですが、今は、1週間後の「期末テスト」に向けて、勉強するのみです。
5教科は、「診断テスト」の勉強をしていれば、出題範囲も重なっている部分もかなりあるので、そんなに慌てることはありません。それに、「期末テスト」向けの「勉強会」は、2週間前から行っています。
とはいえ、部活が休みになったのは今日からでしょうから、本格的な勉強のスタートです。夕方から、自習室にもやってきて、勉強を進めていました。
一方、三木高生は、明日から「期末考査」。午後2時前から自習にやってきた塾生も多かったです。高校生は、長時間学習がトレンド。4~5時間は普通。7~8時間勉強して帰宅した塾生も何人かいました。現学年の評定が決まる最後のテスト。テストが終わるまで、自習室は休みなく開いています。
「個別演習型指導」は、こんな中学生に向いています
2025年02月11日
TOP進学教室が取り入れている「個別演習型指導」は、一斉指導でもなく、かといって、1:3のような個別指導でもありませんが、私がすべての生徒の学習理解度、進度を把握して、学習内容を指示しています。
「個別演習型指導」が向いているのは、
・ 一斉指導ではなく、もっとどんどん先に進みたい。
・ 理解できるところは自分でやって、分からないところのみを教えて欲しい。
・ 問題演習をすることで、得点力を上げたい。
・ 周りを気にすることなく、自分のペースでどんどん進めたい。
・ 定期テスト向けの勉強は自分でできるので、診断テストや入試向けのレベルの高い勉強がしたい。
・ 高松高校、高松一高を目指し、将来は国公立大学、難関私大に進学したい。
・ 静かな環境で、集中して勉強したい。
と思っている中学生です。
無料体験授業をご希望の方は、https://www.topshingaku.jp/contact/
自己推薦入試
2025年02月10日
今日は、公立高校の「自己推薦入試」の合格発表日でした。
これは毎年受験生には言っていることで、今年も先週土曜日の授業時に言いました。
「合格した人も、そうでない人も、これがゴールではない。合格した人は、これでとりあえず高校受験は終了かもしれないけれど、一般入試を受験する人は、これからの1か月で猛烈に力を伸ばしてくる。合格したからといって、手を抜いていると、高校入学時点では逆に大きく差をつけられていることもある。だから、一般入試を受験するつもりで勉強を続けること。一方、合格ではなかった人は、これから先1か月間実力を伸ばすチャンスを与えてくれたと思って、勉強すること。これからの1か月が一番力が伸びる。」
また、塾生たちは、この先大学受験もあるのですから、高校受験でゴールということはありません。まだまだ通過点。通過点を先に通過したか、後になったか、だけの違い。
両者とも、各自の目標に向けて、頑張るのみです。
高2生は、志望大学の赤本(過去問)を今、買え!
2025年02月09日
高2生は、受験まであと1年。と思ったら、すでに、「共通テスト」までは11か月になっています。
高2生にとって、この1月、2月は、毎週末、テストに追われて、あっという間に時間が経つのです。
ですから、気づいたら、「共通テスト」まで11か月・・・、ということに。
この時期におすすめするのは、志望大学の赤本(過去問)を買うことです。
買って机の前に置いておくだけでも、モチベーションアップにつながりますし、どういう出題がされているのかも分析できますし、難易度も分かります。今のままの勉強で対処できるのか、よりレベルを上げた勉強が必要なのかもわかります。
それに、高3受験生は、受験大学の過去問はすでに購入済みでしょうから、高2生が購入することで、品切れなどで現高3受験生に迷惑をかけることもありません。今がチャンスです。書店では、国公立入試が終わり次第、店頭から撤去する場合も多いので、ここ2週間で手に入れておきましょう!
かなり仕上がってきた
2025年02月06日
中3生の「個別演習型指導」では、時間を決めて「入試予想問題演習」をやっています。
ちょっと難しめの問題も入っていて、制限時間内に解くにはコツが必要な予想問題。
1月から練習を重ねてきたので、ミスも減ってきました。また、記述問題も中身がしっかり書けるようになってきています。
何回も塾生には伝えていますが、取れる問題は確実に得点する、これに尽きます。公立高校入試は、同じレベルの受験生が集まるから。同じ得点に何人も、いや場合によっては何十人も並ぶのです。
例年同様、仕上がってきてはいますが、油断禁物。さらに、磨きをかけます。残り1か月。
必死さは必要
2025年02月05日
高校受験、大学受験共に、すでに入試は始まっています。
毎年思いますが、「受験生自身の必死さ」は、必要です。 「何とかなるだろう・・・」みたいな甘えた考えは、ダメです。
結果的に「何とかなった」受験生は、必死にやった結果だと思います。
入試自体は、上位から〇〇人合格、という相対的なもので、△△点以上取れば合格、という絶対的なものではありません。
その〇〇人の中に入れるかどうかは、やはり自らの力で勉強して達成して欲しいと常日頃思っています。
入試というのは、ライバルとの戦いではあるけれども、自分との戦いです。そうした競争を通じて、人生経験上、得るものは多いと思います。
2月に入って、高3生は学校が休みになっても、自習に来ています。必死に自分と戦ってる様子が分かります。私立入試は真っ只中ですし、国公立大学の願書締切も今日です。国公立前期入試まであと20日、自分との戦いに勝ってほしいと思いますし、サポートに徹していきます。
なぜ、個別演習型指導なのか?
2025年02月04日
TOP進学教室は、あくまでもメインは、「個別演習型指導」です。一斉授業で「分かる」のは当たり前です。でも、それは、「解ける」「できる」のとは、異なります。 ですから、「解ける」「できる」までやるのが、「個別演習型指導」です。テストでは、「解ける」ことが得点につながるからです。いくら「分かってる」と言った所で、答案に書けていないと得点にはならないのですから。
教科や通塾回数は選べますが、週1回の通塾では1教科が原則です(中学生の場合)。学年が上がるにつれて、解くのに必要な時間も長くなりますので、中2生以上の場合、「週1回通塾で2教科以上の受講」は基本的にはお断りしています。単にやっただけになるからです。「解ける」「できる」レベルまで持っていくには、時間が必要です。
学校の成績が上位でも、高校進学後、また大学受験時のことを考えて、個々に、取り組むべき問題は変えています(レベルを上げる)ので、易しい問題で時間をつぶすようなことはありません。
なお、「個別演習型指導」では、演習する時間が長いため、受講基準を定めています。学習効果が得られると判断した成績基準以上の方に受講していただいております。
新年度の予約は承っております。事前の面談が必要ですので、お早めにご連絡お願いいたします。