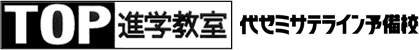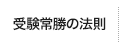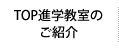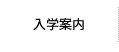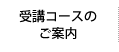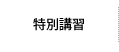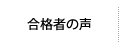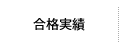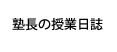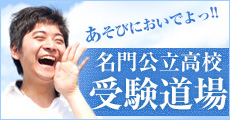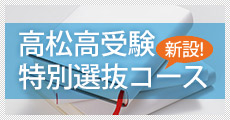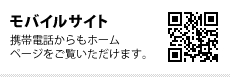なぜ、個別演習型指導なのか?
2025年02月04日
TOP進学教室は、あくまでもメインは、「個別演習型指導」です。一斉授業で「分かる」のは当たり前です。でも、それは、「解ける」「できる」のとは、異なります。 ですから、「解ける」「できる」までやるのが、「個別演習型指導」です。テストでは、「解ける」ことが得点につながるからです。いくら「分かってる」と言った所で、答案に書けていないと得点にはならないのですから。
教科や通塾回数は選べますが、週1回の通塾では1教科が原則です(中学生の場合)。学年が上がるにつれて、解くのに必要な時間も長くなりますので、中2生以上の場合、「週1回通塾で2教科以上の受講」は基本的にはお断りしています。単にやっただけになるからです。「解ける」「できる」レベルまで持っていくには、時間が必要です。
学校の成績が上位でも、高校進学後、また大学受験時のことを考えて、個々に、取り組むべき問題は変えています(レベルを上げる)ので、易しい問題で時間をつぶすようなことはありません。
なお、「個別演習型指導」では、演習する時間が長いため、受講基準を定めています。学習効果が得られると判断した成績基準以上の方に受講していただいております。
新年度の予約は承っております。事前の面談が必要ですので、お早めにご連絡お願いいたします。
持久戦
2025年02月03日
範囲の狭いテストは別として、中学生の「診断テスト」や「高校入試」、高校生の「校外模試」や「大学入試」になると、短期間の勉強では成績は上がりません。継続した学習が必要です。今日勉強したところばかりが、そうしたテストに出る訳ではないですから。
これまでの指導経験上から言えば、なかなか成績が上がらなくても、あきらめずに正しい方法で学習に取り組んでいれば、あるときから一気に理解力が上がり、得点力がアップします。簡単な例を挙げれば、英単語でしょうか。
日々少しずつ覚えていっても、覚えたものがテストに出るわけではありませんが、それが100日、200日と継続され、1000単語、2000単語分かるようになれば、英文も読めるようになるということです(もちろん、単語が分かるだけで読めるようになるわけではないですが)。
逆に、「1日くらい勉強やらなくてもいいかな、明日やればいいし・・・」と考える日々が続くと、一気に理解力が下がります。
そしてそれを取り戻すのは大変なのです。特に、高校生・・・。
ですから、高校生になったら、日々の学習は絶対に必要です。高校受験も終わっていないのにこんなことをいうのもあれですが、高校に合格したら、いや、高校入試が終わっても、継続した学習必要です。春休みに遊びすぎると、一気に理解力が下がってしまいます・・・。
新高1生は、高校内容に先行するために、春期講習で、英語・数学は、発展的な内容まで指導します。日程等、詳細はしばらくお待ちください。
37回目の中3生
2025年01月30日
公立高校入試まで、あと1ヶ月あまり。
実は、この1ヶ月間が爆発的に得点力が伸びる時期です。
今年の中3生は、私が指導する37回目の中3生ですが、これまで36年間の中3生を見てきても、それは毎年思うことです。
受験校が決まり、私立高校入試も終わり、公立高校入試対策に専念できます。また、中学校での学習内容もほぼ終わり、自習の時間も増えることもあります。
まだまだこれからですよ。「診断テスト」の点数は、入試の合否判定には使われませんからね、使われるのは本番の点数です。やったもん勝ちです。
集中して学習できる自習室も完備して、TOP進学教室は受験生を応援しています。
「数学が・・・」
2025年01月29日
毎年のことですし、毎年書いてる気がしますが、中3生の秋以降、数学の点数が伸び悩む場合があります。
定期テストは、得点できても、「診断テスト」で点数が伸びないのです。秋以降、問題自体が難しくなっているのも一因ですが、数学の勉強自体が、「定期テストレベル」でとどまっている場合が多いのです。要は、「解法の暗記」になってるのです。
それでは、未知の問題に遭遇したときに、全く手が出ません。方程式の文章題、関数の動点問題、相似と三平方の融合問題など、それなりに難しくてもチャレンジすることが必要です。そして、解法の暗記ではなく、解法を理解して解くことが大切です。
中3生の「特別選抜コース」では、そうした問題に対処できるように、解法の指導を行っています。定期テストレベルの問題は指導していません。それよりもレベルの高い問題を教えています。ですので、「診断テスト」でも、満点を取ってくる塾生もいます。そういうレベルの指導です。
毎年、春期講習から、そうしたレベルの内容を指導していますので、新中3生は「春期講習」からの受講をお願いします。
(途中からの受講の場合には、「診断テスト」「入試」を解く上で必要な解法が抜け落ちます)
合格可能性判定は、あくまでも目安
2025年01月27日
国公立2次試験に向けて、大学受験生は勉強をやっています。各社の「共通テストリサーチ」の結果を見て、出願するわけですが、その判定を鵜呑みにするのはどうか、と思います。
もちろん、1次と2次の配点比率や試験教科の得意、不得意状況等により、その判定を重視せざるをえない場合はあります。ですが、A判定なら100%合格する、とか、E判定なら合格できないとか、そんなことはないはずです。あくまでも目安です。
毎年の各大学の合否状況を見てみると、BやCだと合格者もいれば、不合格者もいます。いわゆるボーダーライン上では、合格者と不合格者の人数はほぼ同じくらいです。ボーダーラインよりも下でも合格者はいますし、逆にボーダーラインを上回っていても、合格していない者もいます。要は、1次で決まるのではなく、2次勝負、ということです。
何回かこの日誌にも書きましたが、E判定からの合格を勝ち取ったある塾生の話です。(E判定からの合格は、皆さんが想定されている以上に、たくさんあります!)
その塾生は、センター試験で思うように点が取れずにE判定でした。ですが、将来就きたい職業の目標を変えることなく、予定通りの大学を受験することにしました。ですが、合格するには、2次試験でほぼ満点をとるくらいでないと厳しい、という判定でした。2次試験に向けて、私の指導が始まりましたが、満点を目指すにはそれなりのレベルと量が必要ですので、かなりの負荷は与えたと思います。それにくらいついて、頑張って勉強をしてくれました。
合格発表の当日、そのころはまだネット発表とかが普及していなかったので、合格発表の掲示板を見て、塾に合格の報告に来てくれました。その時には、すでに学校にも報告に行ってたそうですが、学校の先生に合格の報告をしたところ、
「え?? もう一回掲示板見て確認してこい!」
って言われたそうです。信じてもらえなかったそうで・・・。
入試の出来具合を聞いてみたら、ほぼ完答できたということで、それが勝因でしょうね。
最後まで合格目指して勉強することに尽きます!!
成績が上がるのは授業を受けている時ではない
2025年01月22日
成績が上がった、できるようになった、と実感するのは、授業を受けている時ではありません。
では、いつなのか?
それは、自分で問題を解きなおしたり、解説を読んで考えたり、また、教科書や参考書で調べたり、そうした時に、「ああそうだったのか」「分かった」「解けた」「できた」と実感できるのです。
ですから、TOP進学教室は一斉授業を基本的には行っていません。受け身的になってしまいますからね。
自分で調べたり、考えたりする時間を確保できる、「個別演習型指導」を行っているのは、その為です。
したがって、一斉授業で隅から隅まで「教えてもらいたい」人には、TOP進学教室は向いていません。
あくまでも、自分の力で考えることを重視しています。
高松高、一高、三木(文理)を目指します
2025年01月21日
TOP進学教室の中学部は、「高松高校・高松一高・三木高校(文理)レベル以上」を目指す人向けです。
それらに合格できるような指導体制をとっています。いわゆる一般の塾とは違うところもたくさんあります。その点は、事前の面談等で説明させていただき、納得されてから入塾をお願いいたします。なお、入塾時には、成績基準がありますので、それを超えていることが必要です。
内申点200点とは?
2025年01月20日
高松高校に合格するには、内申点は200点以上は確保したいものです。(220点満点)
計算式は、
中1 5段階×9教科 = 計45点
中2 5段階×9教科 = 計45点
中3 (5段階×2)×5教科 = 計50点
(5段階×4)×副教科4教科 = 計80点 の 合計 220点 です。
もし、中1~中3まで、オール4だとすると、内申点の合計は、 176点 です。
したがって、200点を確保しようとしたら、少なくとも4と5を半々ずつ取る必要があります。
(中3時の5教科は2倍、副教科は4倍する関係上、多少のずれはあります)
定期テストや診断テスト、また日頃の勉強は、5教科メインの人が多いかもしれませんが、副教科も重視して日々の学校の授業に取り組む必要があります。
(仮に、中1~中3まで、副教科がオール4で、5教科がオール5の場合には、内申点は196点になり、200点に届きません)
共通テスト、香統模試、高1高2共通テストチャレンジ
2025年01月19日
「共通テスト」が終わりました。受験生の皆さん、お疲れさまでした。
自己採点に基づく、「共通テストリサーチ」の結果が判明するまでは、まずは2次試験に向けて、勉強スタートです。「共通テスト」だけで決まるわけではないですし、2次の方が配点が高い人も多いですからね。あれこれ考えている時間があったら、それを2次に向けての勉強時間に充てた方が、合格は近づきます。
高3生以外の、高1、高2生は「共通テストチャレンジ」でした。1日で実施しましたので、かなり疲れたと思いますが、「共通テスト」のレベルは体験できたはずです。解説授業も受講できますので、解けなかったところは復習です。今後の勉強の方針は、成績表を個別に返却するときにアドバイスします。
また、中3生は、入試に向けた最後の「香統模試」でした。解答解説集は、その場で配布しましたが、「できた」「できなかった」では、先につながりません。解けなかった問題を復習して、次に同じような問題に出くわしたときには、必ず解けるようにしておきましょう。それに、明日は「総合診断テスト」がありますので、今日中の復習は必須です。
明日は「共通テスト」
2025年01月17日
明日から「共通テスト」。
受験会場の下見を終えてから、最終チェックのために自習室にやってきた高3生もいました。
高3受験生に、これまでに指示したことですが、
「いつも通りに、沈着冷静に。」
気負わず、いつも通りにやれば、勝てます。
健闘を祈っています。