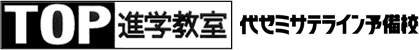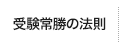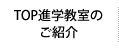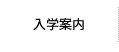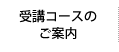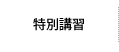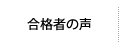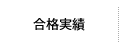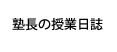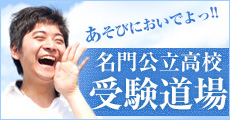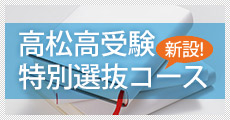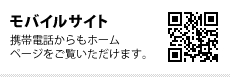夜に勉強するのは皆同じ
2020年07月06日
今年は、夏休みが短縮され、学校では、午後にも授業があるところが多いようです。つまり、普段と変わらない生活が続くということになるのでしょうが、受験生は違いますよ。夜に勉強しようと思ってるなら、それは失格です。もちろん、夜に勉強することは必要なんですが、夜だけではダメです。一番大切なのは、夕方の時間の使い方です。これまで、部活に充てていた時間ですね。これをそのまま勉強時間に充てることです、重要なのは。眠いから無理! って人は、多少の仮眠はいいでしょうが、10分から15分まで。仮眠したら、即勉強です。
あのですね、時間の使い方の下手な人は、期限を区切ってないんです。「〇時から勉強しよう」とか、決めてないのです。きちんと決めてください。それが、無理な人は、自習室へ来ればいいだけです。勉強できる環境が、そこにはあります。
やりすぎ?
2020年07月05日
昨日、今日と、中学生の「テスト対策勉強会」でした。
統一した休憩時間はあるのですが、みんな休憩時間も勉強してました・・・。ちょっと、やりすぎかな? 休憩も大切ですよ。ちなみに言っておきますが、「勉強会」は自主的に参加するものですので、強制参加ではありません。家で集中して学習できるなら、家でやればいいのです。塾の方ができる人は、塾に来ればいいだけのことです。トップ高校、大学を目指すのですから、そのくらいの判断はできるはずですから。
代ゼミサテラインは、都合に合わせて受講が可能です
2020年07月04日
今年は、夏休みが短縮され、「共通テスト」の対策に時間が十分とれないと思っている受験生もいるかと思います。
代ゼミサテラインの「夏期講習」では、「共通テスト」全教科に対応しています。また、受講時間帯は都合に合わせて決められますから、学校帰りに寄って受講する、とか、学校が休みの日に集中して受講する、などが可能です。忙しい今年の受験生には、活用できるはずです。
「定期テスト」の「過去問」しません
2020年07月03日
塾生からはこんなこと聞かれることすらありませんが、「定期テストの過去問はしません」。
定期テストで、過去問に頼る勉強法は非常に危険です。確かにその時は点が取れるかもしれませんが一瞬ですから、頭の中に定着はしません。後々、範囲が広い「診断テスト」「入試」の時に、全く歯が立たないことになってしまうのです。日々の学習を行い、教科書の隅々まで目を通し、学校の教材を理解して、反復して取り組めば、きちんと定着します。時間はかかるかもしれませんが、そのかけた時間分は知識として残るのです。
「定期テスト」の過去問指導を希望される方は、他塾をお薦めします。
誤解しないでいただきたいのですが、「入試」の過去問指導はします。中学校3年間の学習内容が出題範囲ですし、出題傾向もあります。効率よく学習し、得点力を上げるためにも、過去問は活用します。基礎基本を身につけるために行う学習とは、性質が異なるからです。
テスト発表
2020年07月02日
三木中学校では、今日、「テスト発表」でした。
学校が再開されてから1か月余り。学校の授業進度はかなり速くなっています。例えば、三木中学校3年生の今回の英数のテスト範囲の最後のページは、昨年の「1学期期末テスト」と、ほぼ同じです。実際には、去年のテストは、6月19日、20日でしたので、単純に比べることはできませんが、去年は2か月かけて進んできたところを、今年は1か月ちょっとで進んできたわけですから、やはり進度は今年の方が速いです。なおかつ、昨年は、「中間テスト」「期末テスト」の2回テストがあったものを、今年は1回のテストですから、今回のテスト範囲は広くなっています。去年よりは。
ということは、効率よく勉強していかないと、時間不足になるわけで、早め早めの取り組みが大切になってきます。
TOPを目指すのです!
2020年07月01日
TOP進学教室という塾名は、「TOP」レベル高校、大学への進学を目指す、ということで、決めたものです。ですので、そういう意欲を持った生徒の入塾を期待しています。
夏期講習ですが・・・
2020年06月30日
「夏期講習」は、7月22日から開講しますが、学年、コースによっては満席の曜日、時間帯があります。「夏期講習」のみを受講ご希望の方は、お早めにお問い合わせください。
勉強会
2020年06月29日
この土日に、テスト対策の「勉強会」を行いました。中学校のテストまでは、10日ありますが、それを「まだ10日もある」と考えるか、「あと10日しかない」と考えるかで、勉強への取り組み方は大きく変わってきます。
基本的に、土日は勉強し放題の時間、というのが私の考えであるので、土日の時間は効率よく使うべきですね。
全国模試
2020年06月27日
高校生は、例年同様、高校で全国模試を受験する時期になりました。
その直前になって、「対策はどうしたらいいですか?」と聞かれても、これだけやっとけばバッチリ、みたいな回答はありません。部活の大会1週間前になって、「勝つには何を練習したらいいですか?」という類の質問と同じ。
範囲の広い全国模試は、日々の学習の積み重ねがないと太刀打ちできません。まずは、学校の宿題なり、指定参考書なりを日々取り組むことです。それをやらずして、直前だけで・・・、というのは、無理です。
出題者の意図をよみとる
2020年06月26日
模試にしても、入試にしても、出題の意図 があるわけです。
解説解答を見て、「ああそうだったのか・・・」と納得するのは簡単です。
ですが、それを実際のテスト中に感じ取ることができるようになると、問題はスラスラ解けるようになります。そこまでの領域に達するには、それなりの学習量が必要ですが、高校入試くらいなら、「ここでひっかけようとしているな」とか、「ここで計算ミスしそうな問題だな」とか、感じ取ることは可能です。
あまり勉強していない受験生の場合には、そこでことごとく引っかかるわけで、点数が伸びないわけです。逆に、勉強ができている場合には、そこで出題者の意図を感じて、「そうきたか・・・」と納得しながら解いて、正解に至るのです。
ことごとく引っかかってしまっているかどうかは、数学であれば、途中式を見れば分かります。