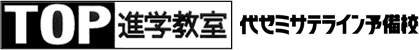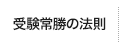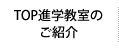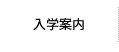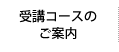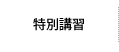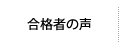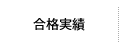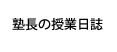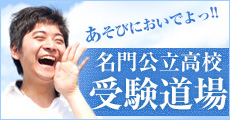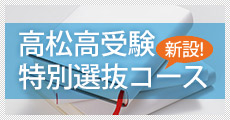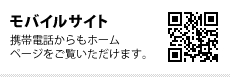数学を捨てると選べる範囲が狭くなる
2018年06月12日
高校になって、数学の難しさに驚く高校生は多いです。中学校の時のように、見たことがある、解いたことがある、パターンを当てはめたら解ける、といったような問題が少なくなるからでしょうし、「場合分け」という難敵を攻略できない場合も多いからでしょう。
数学を捨てて、文系に進むという場合もあります。ですが、そうなるとほとんどの場合、私大文系になります。一部の公立大学などでは、数学なしでも受験できますが、数は限られてきます。また、早稲田大学の政経学部が、入試で数学を必須にすると先日公表しました。この流れが広がるかどうかは分かりませんが、私大文系でもそういう大学も増えるかもしれません。
話はずれますが、去年、今年と、大都市圏にある難関私大の合格者数は絞り込んで発表されています。政府の方針で、定員を大幅に超える入学者数がいる場合には、政府から大学への補助金をカットされてしまうからです。国公立大学への進学者、他大学への進学者等の手続き状況を見ながら、追加合格を出しているところも多いです。補欠合格者を数十名発表しておきながら、繰り上がり合格ゼロ(つまり、補欠合格でも入学できない)というところもあります。
模試でA判定やB判定をとった場合でも合格できない例もあるようですし、また、難化を懸念して、出願時にレベルを落として出願する例も多くなり、そうした大学もこれまでよりも合格しにくくなっています。
数学を捨てて、科目が少なくなったから楽かというと、そうではなくなってきています。
普段からやっていればいつでもできる
2018年06月11日
テスト勉強で疲れるのは、普段勉強していない証拠です。
確かに、短期間でたくさんのことを詰め込まなければならないでしょう。でも、それは普段から学習している内容です。習ったときに日々取り組んでいれば、そんなに時間をかけなくてもできるはずです。それを溜め込んでしまうから、テスト前に一気にやらなければならなくなり、睡眠時間も短くなり、疲れ果ててしまうのです。
日々、計画的に学習していれば、テスト前に慌てることはありません。普段通りのことをやればいいだけです。テスト前日も遅くまで起きて勉強しなくてすみます。睡眠不足にもなりません。
これは、部活でも同じですね。日々の練習を手抜きして、大会やコンクールの1週間前に必死になっても遅いのと同じです。勉強も部活も何でも、日々の積み重ねに勝るものはありません。
勉強会
2018年06月10日
三木高校は、明日から、「前期中間考査」です。また、中学校も、10日後から「期末テスト」です。
今日は、午後から、「勉強会」を行いました。中学生は部活がまだあり、そんなに多くは来ませんでしたが、ほぼ満席の状態でした。
中学生からはほとんど質問は出ませんでしたが、高校生からは、数学、英語、化学の質問があって、それに個別に解説しました。明日からも、テスト帰りに、自習室は利用できます!!
例年のことですが・・・
2018年06月09日
高1生は、高校に入学して2ヶ月。高校の勉強が、中学の勉強とは大きく異なることに、戸惑いながら勉強している感があります。
3月の春期講習前に行った「高校学習ガイダンス」で、そのギャップを事前に伝えていたはずなんですが、現実に直面すると、あまりのギャップに驚いているようです。
中学校内容であれば、塾で全部授業で教える時間的余裕もありますが、大学入試に関する内容を授業ですべて教えることは時間的に不可能です。ある程度は自学が不可欠です。高校生になったら、高校入試の時以上に、自学の時間は増やすべきです。ですから、高校からも、指定参考書の課題が出されていると思いますが、それは自学で学んで欲しいという意味だと思っています。
ですから、高校や塾で、単に授業を受けて理解しました、では通用しないわけで、それを踏まえてどれだけ自学に取り組めたかで、結果は大きく異なってくると思っています。
高校で成績が伸び悩んでいる場合のほとんどは、勉強時間不足です。自学不足ですね。高校生が新規に入塾する場合の面談で、「塾の授業に来る回数は減らしてもいいので、その代わりに自習に来てください」と、普通の塾なら言わないようなことも平気で私は言います。まず何が必要かを判断した上で、そう言っています。
調べたら分かる
2018年06月08日
個別演習型指導では、個別に分からないところを教えますが、調べたら分かることは調べさせます。親切心をさらけだして教えすぎてしまうと、教わることに慣れてしまう、他の表現を使えば、受身になってしまうからです。
難解な漢字の読みを聞いてきた高校生がいましたが、それは調べれば分かることです。何のためにスマホ持ってるんでしょうか・・・・?
小学生なら、特に、漢字の読み書きは、国語辞典、漢字辞典で、語句に関す問題は、たとえば、ことわざ辞典や反意語辞典などで調べさせます。というか、そんなことは言わなくても、自然と本棚のところに行って調べていますが・・・。とはいえ、入塾してすぐの頃は何で調べたらいいのかは分かりません。ですから、「こういう場合は国語辞典、こんな場合には、漢字辞典のここを見る」とか、教えます。そうしたら、いつのまにか、調べる方法を身につけて、一人でできるようになってるのです。
テスト勉強不要論
2018年06月07日
タイトルの表記が最適かどうかは分かりませんが、日々の学習をきちんとやっていれば、テストの前に、部活まで休みにして、「テスト勉強」をする必要はない、とずっと思っています。「定期テスト」に出題されるのは、学校の授業で習った内容であって、そんなに極端に難しいものでもなく、また、範囲も決まっています。テスト1~2ヶ月前までの内容です。日々の勉強の積み重ねで、クリアできるはずです。
ただ、問題になるのは、その日々の勉強の中身というか、達成度ですね。単に教科書読んで終わりとか、ノート整理して終わりとかでは、ダメです。学校指定の問題集を、いつ解いても解ける状態にする、というようなレベルが必要と思います。1日に3時間くらい勉強すれば可能と考えます。
テスト前に部活を休みにして、その時間で「テスト勉強」ができるようにしているのは分かりますが、それをあてにして、日頃の勉強が疎かになるのでは困ります。テスト前は、日頃の勉強の再確認くらいで、さっとテスト勉強が終わるのが理想です。
明日は 「診断テスト」
2018年06月05日
中3生は、明日、「診断テスト」です。
今日も、明日のテストに向けて自習に来ている中3生もおりました。
中3生には、春期講習以来、ずっと、「定期テストと診断テスト、どっちが重要か?」を言っています。
当然、○○テストです!
中3「特別選抜コース」 「選抜コース」
2018年06月02日
今日の授業で、中3「特別選抜コース」「選抜コース」の1学期の授業は終了です。
春期講習から、中1内容の指導を行ってきました。来週に行われる「第1回診断テスト」に向けて、です。中1の内容は、それほど難しいところはありませんが、意外に忘れているところがあるかもしれませんので、残り数日で最終チェックが必要です。
中3「特別選抜コース」、「選抜コース」は、夏期講習より再開します。中2内容の指導に入ります。入試にも頻出の内容がたくさんあります。一次関数、証明、電流、化学変化、英作文、長文読解などをメインに指導を行います。一気に指導レベルが上がります。
「期末テスト」が終わって、夏休みが始まるまでは、思いっきり部活に励んでください!!
「型」は必要だけれども・・・
2018年06月01日
高校生の数学では、「場合分け」が重要です。
ある程度、「パターン分け」というか、「こういう場合にはこうせよ」みたいな解法はあります。ですが、それを丸暗記してたら、それから外れた問題の場合に解けなくなります。「こんなのやったことない」と。
ですが、大学入試ではそうした問題も出題されることがあるわけで、その場で考えて、答を出さなければなりません。
重要なのは、場合分けの「こういうときにはこうする」といった解法を覚えるだけではなく、「なぜここで場合分けをするのか?」ということを考え、自分で納得できるまで考えることだと思います。
差
2018年05月31日
中1生の「中間テスト」の結果が返ってきました。
毎年そうですが、「中間テスト」は出題範囲が狭く、内容も簡単なので、高得点が取れます。ですので、点数の差がつきにくいです。ですから、自分では「頑張った」と思っていても、結果の順位を見て愕然としたり、不満に思ったりすることもあるかもしれません。
ですが、順位の差はあっても、力の差はあまりありませんので、悲観的になる必要はありません。
次回の「期末テスト」に向けて、勉強を開始すれば、たとえ今回は思うようにいかなかったとしても、挽回は可能です。