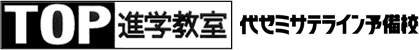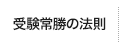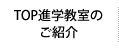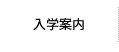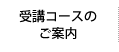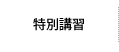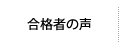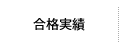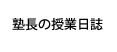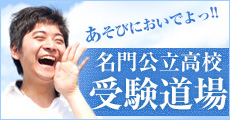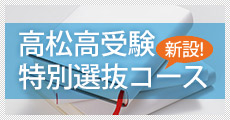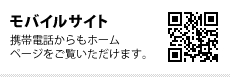体験授業の重要性
2018年07月03日
体験授業は重要です。最近は、夏期講習も近づいてきたので、増えてきていますが、受講を検討している場合には、受けたほうがいいです。
授業の方式、レベル、先生との相性など、確認すべきですね。 自分には、合わないと判断したら、申し込むべきではありません。他塾をあたるなり、他の方法での学習を探すなりすべきです。
車を購入するときは試乗、洋服を買うときには試着、お土産売り場では試食、などお金を払う前に試すことはやっているはずですので、入塾する前に是非お試しを。
特に、高3生は、体験授業後、入塾を即決しようとする場合がありますが、「待って、もう一回体験に来てください。」と、納得してから入塾してもらうことも多いです。
図や表、グラフにする
2018年07月02日
数学や理科の質問で困るのは、自分の考えを図や表、グラフにしていないことです。まぁ、解けない原因のほとんどはそれです。
目で見える形に整理していないから、頭の中で処理しきれなくて、「分からない」 となるのです。
数学の方程式の文章題でも、高校生の順列、組み合わせの場合でも、「目で見える」ように、図や表、グラフ化すれば、解けます。質問に答えるときも、図や表、グラフ化して説明します。
そのためには、問題文で与えられている条件を図、表、グラフ化する力は必要になります。でも、人に見せるわけではないですから、そんなに難しくはありません。
【夏期講習】 中3特別選抜コース 理科授業レベル
2018年07月01日
夏期講習の 「中3特別選抜コース」 の理科では、難易度の高い問題を中心に授業を進めます。
「診断テスト」や「入試」で、配点が2点となるような問題を解けるようにします。2点配点の問題は、50点満点中、数問しかありませんので、基本的には、満点を狙う生徒対象の授業です。基本的事項は理解しているものとして、授業を進めます。
高松高校・高松一高は、来週から「期末考査」
2018年06月30日
高松高校・高松一高は、来週月曜から「期末考査」です。
今日の自習中、また授業中に、質問に答えましたが、「そこ、いい質問!」と言えるような質問が多かったです。勉強しているからこそ出てくる質問でした。
明日も、午前中自習室オープンです。
【満席講座のお知らせ】
2018年06月29日
夏期講習講座の 「国語読解解法の奥義」 は,講習のみ受講者用の席が満席となりましたので、講習生の募集を終了いたします。
(塾生用の席は若干あります)
キャンセル待ちのみ受付いたします。
28日(木)夜にご連絡くださった方へ
2018年06月28日
連絡先が不明の為、お手数ですが、再度ご連絡をお願いいたします。
高校生の一斉授業はしていません
2018年06月27日
高校生の指導法に関してですが、一斉授業形式での指導は行っておりません。
理由は多々ありますが、授業を受ける高校生にとって、最適な指導法ではない、と私が判断しているのが最大の理由です。
お問い合わせありがとうございます
2018年06月26日
夏期講習のお問い合わせ有難うございます。
順次ご連絡しております。また、案内書も順次お送りしております。到着まで今しばらくお待ち下さい。
なお、夏期講習ですでに満席になったコース、満席に近いコースも出ております。受講ご希望の場合には、お早めにご連絡をお願いいたします。体験授業は、7月14日までです。人数の関係上、ご希望通りにならない場合もありますので、お早めにご連絡お願いいたします。
(サテラインの体験受講は、7月14日以降も可能です)
テストの後が肝心
2018年06月25日
中学生の期末テストの答案もそろそろすべて返ってきた頃でしょう。大事なのは、点数ではありません。復習をすることです。
間違った問題はどこから出題されているのか、教科書のどこに載っているのか、なぜ自分は間違ったのか、こうした点を問題用紙、解答用紙、解説(あれば)から、分析しなければなりません。定期テストは、学習したことの理解状況の確認がメインですから、どこかに出題の元があるのです。それを分析した上で、次回のテスト勉強をやる上での修正点を見つけていくのです。
これは、テストの終わった後に限りません。日々取り組んでいる宿題や、問題集でも同じようにしなければなりません。
そうした「間違いなおし」がきちんとできていない場合には、TOP進学教室では、厳しく指摘します。間違っているのにマルがついている、文字が乱雑で読みにくい、間違っている問題の直しはできているが、途中式がない(数学)、などは、ノートチェックした後、返却時に指摘します。状況が悪い場合には、その場で直させます。
ノートは私がすべてチェックしています。問題を解いて間違っても、私はあまり何も言いません。ですが、「間違いなおし」のいい加減さは、厳しく指摘します。間違っているところを、解けるようにしないで、向上なんてありえないですから。
こうした修正ができるのは、早いほうがいいです。高校生よりも中学生、中学生よりも小学生の方が、修正しやすいですし、向上もしやすいです。学年が上がれば上がるほど、自己流の間違った学習法はなかなか修正できません。
入試のレベルに合わせる
2018年06月23日
入試に合格するには、いつまでも自分のレベルに合った問題の指導を受けているのではダメです。確かに、自分の理解できる問題の指導を受けていれば、理解もできるし、解けるし、力がついたと実感できるでしょう。
でも、それでは合格はできません。なぜなら、入試は「自分のレベル」には合わせてくれないからです。受験生の方が、「入試での合格レベル」に合わせた勉強をする必要があります。
ですので、TOP進学教室では、中学生にも高校生にも、塾生個々の志望校のレベルに合わせた指導をします。ちょっと難しい問題もあるかもしれません。でもそれを乗りこえないと、入試の合格レベルには到達しません。「分からない」状態のままでは、今の自分のレベルを超えることはできていないのです。