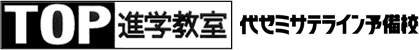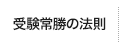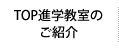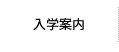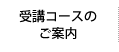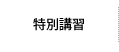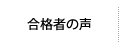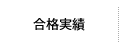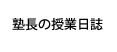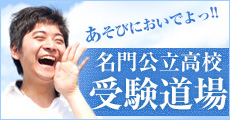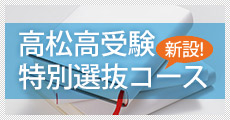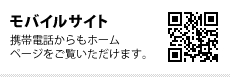3連休
2014年11月21日
明日から、3連休です。
が、中学生、高校生には、絶好の勉強日和・・・。自習室も、午前中から、もちろん開放します。
高3生は、大学推薦入試の塾生も複数います。センター模試の塾生もいます。
進路に関して、ある程度の方向性が決まる3連休です。全力で臨みましょう・・・!!!!
冬期講習
2014年11月20日
まもなく詳細はアップしますが、中学生は、【選抜制】です。受講には成績基準があります。また、選抜テストも受験してい
ただきます。高松高校・高松一高・三木(文理)レベルの指導です。
高校生は、国公立大学、難関私大志望者を対象としています。
小学生は、附属中学受験、ならびに、高松高校・高松一高を目指しています。
志高き受講生を求めています。なお、募集は若干名です。満席のコース、学年もありますので、ご了承ください。
昨日に続いて
2014年11月18日
昨日に続いて、質問の仕方です。 私は基本的には、質問に来た塾生には、塾生自らの言葉で説明させるようにして
います。
「先生、この問題のここからが分かりません。」
「え~っと、どこかな。これね。その前のこの式はどうして、こうなると思う?」
「前の式を変形して、もう一つと連立すれば、交点が出ると思います」
「そうだね。交点がでれば、座標が分かるよね。そしたら、他に分かるところはない?」
「え~と、辺の長さが分かります。そうか、分かりました!」
というような具合で、最後まで教えなくても、ちょっと誘導するだけで、自分で解決できること多いのです。もうそれ以上、
教えなくてもいいですよね。自分で分かったわけですから。
最初から最後まで教えるのが親切丁寧な指導かもしれませんが、「分かる」だけで留まるように思うのです。大切な
のは、自力で解けるようにすることだと思います。ですから、極力、自分で考えることを重視しています。その点が、親切
丁寧な他塾との違いかもしれませんが、「自力で解ける」ことを目標としている以上、このスタンスは変わりません。
質問の仕方
2014年11月17日
テスト前になると、いつもにも増して、質問が増える。質問があるということは、勉強している証だと思うので、それ自体は
いいことだと思っている。ただ、成績が向上する「質問の仕方」というのはある。
「先生、この問題分かりません。」
これは、良くない質問の仕方。
私が望む質問の仕方は、
「先生、この問題なんですが、〇〇のところまでは分かるのですが、その後が分かりません。教科書や参考書でも調べ
たのですが、分かりません。どうしてこの式が導かれるのですか?」
あくまでも例なので、この通りでなくてもいいが、「どこまで分かっているのか、どこからが分からないのか。」を伝える
質問がベスト。なぜなら、教えるほうとしても、どこを重点的に教えればいいかが分かるし、質問する方としても、
自分の疑問点をはっきりとさせることができるから。 きちんと勉強していたら、こうした質問にはなると思う。
質問するときには、是非この仕方で・・・。
やはり午前中
2014年11月15日
勉強するなら午前中。
今日は、午前中から自習室利用できましたが、利用者が少ない・・・。三木中学校は、学校があったので、当然誰も来
れませんが、高校生は来れるはずですが。 学校の土曜開放に行ってたのならいいのですが・・・。 もし今日の勉強の
スタートが、午後からというのは最悪ですよ。
今日は、この後、午後、夜まで自習席は満席です。明日の午前中は満席ですが、午後は2席空いています(今のところ)
週末は・・・
2014年11月14日
三木高校は、来週から「中間考査」。この週末は、勉強し放題ですね。高校の土曜開放なども利用して、集中して学習に
取り組んでほしいと思います。もちろん、自習室は、土日とも朝から利用できます。
中学生は、テストまでまだ時間があるように感じているかもしれませんが、今回は、出題範囲が広いので、これまでの
ようにはいかないですね。数学も図形に入っていますので、問題演習はしっかりとやらなければなりません。もちろん、
中3生は、最後の定期テスト。緩みは許されません。
要注意
2014年11月11日
センター試験対策で、問題演習をしている高3生には毎年注意していることがある。
過去問演習では、問題がないのだが、各出版社から出されている「実戦演習」型の問題集を解くときには注意が必要で
ある。
特に、過去の模試を集めて構成してい問題集の場合、実践型で非常に使いやすいのだけれど、その得点には注意する
必要がある。なぜなら、その収録された模試がいつ実施されたのか、によって難易度は変わってくるからである。例えば、
5月に実施された模試の場合、高3生はまだ部活もあるときなので、受験勉強に本格的に入っていないこともあるので、
本番よりもかなり易しめに作ってある。その模試を解いて、「90点取れた!」と安心するのは、ちょっとマズイと思う。
模試を収録した問題集には、実施した模試の時期も載っているので、それを確認することが絶対に必要。
ということは、本番の過去問よりも、そうした問題集は、易しめの問題も載っているので、過去問を当然ながら解いて、
本番レベルに慣れておく必要がある。
解く順序
2014年11月10日
テストを受けるとき、解く順番は大事です。
塾内でテストをするときに、机間巡視をしていると、最初から順に解いていることに遭遇します。それは別に構わないの
ですが、解く順序を組み立てた上で、そうして欲しいのです。
テストは、最初から易しい問題が並んでいるというわけではありません。数学は、比較的易しい順序で並んでいることが
多いですが、絶対ではありません。理科や社会なら、不得意な分野が最初に来ていると、時間がかかるかもしれません。
設定されたテスト時間内に、より多くの問題を解いて、高得点をとればいいのですから、解く順番は関係ないのです。
まずは、確実に解ける問題から解く。そして、点数を着実に積み重ねていくことです。解きにくい問題は、後で解けば
いいのです。解きにくい問題というのは、他の受験者も解きにくい訳で、実はそんなに差がつく問題ではありません。
点数の差がつくのは、実は基本問題です。それを確実に得点していれば、大きく失敗することはありません。
高得点を目指していて、失敗する例があります。満点を目指している場合です。満点を目指してますから、最後まで解く
のですが、最後の方が難しくて、時間いっぱい使ってしまい、見直すこともないまま、終了。で、結果が返ってきて、思い
のほか、基本問題での失点が多い。その結果、基本問題を確実に解いた人と点数があまり変わらない、ということもあ
りえるのです。
こうした失敗を防ぐためにも、解くための順番を考えることは大切ですし、基本問題を確実に得点することも大切です。
先日、高3生に、「センター試験」英語の解く順番をアドバイスしました。先日の模試で20点UPしたそうです。解く順番を
変えるだけでも、そのくらいは上がります。特に、「センター試験英語」は、最後の長文の配点が50点と高く、1問あたりの
配点も高いので、時間不足は致命傷です。ですから、解く順番を変えたほうがいい生徒も多いのです。
まだ伸びる
2014年11月07日
勉強って、本気になって勉強して、すぐに伸びるものではありません。もちろん、定期テストなどの範囲の狭いものは、
すぐに伸びますが・・・。 中3生が部活が終わって本格的に勉強したとしたら、それまでの成績や定着度合いにもよりま
すが、1~3ヶ月はかかると思います。安定して伸びるようになるまでに。 それまでは、「勉強しても伸びない」「点数が
取れない」といった悩みもあるでしょうが、特に英語や社会は時間がかかるかもしれません。勉強したところがそのまま
出るわけではありませんので。英語なら長文読解、同意文完成などは、1つの学習分野だけの理解では、なかなか正解
には至りません。社会も、用語は暗記しても、資料やグラフの読み取り、年表などが絡んでくると、断片的な知識だけでは
なかなか難しいです。
かといって、何もしなければ、点数は伸びません。勉強したものが、ある程度蓄積されていくと、徐々に問題が解けるよ
うになっていきます。これは、スポーツでも同じでしょう。例えば、野球のピッチャーであれば、カーブを投げれるようにな
った、シュートも投げれるようになった、フォークボールも投げれるようになった、と徐々に球種が増えるにしたがって、打
者を上手く打ち取ることができるようになるはずです。でも、ストレートしか投げられない段階では、やはり狙われてうまく
打たれてしまうでしょう。いろんな球種があれば、作戦も立てやすいはずです。
勉強も同じです。知識が多ければ多いほど、打つ手がたくさんあるのです。しかしながら、どうしても定着するには時間
がかかります。中3生は、11月のテスト結果で、受験校を決めなければならない場合が多いのですが、「診断テスト」の
点数はまだ伸びます。今の段階の点数で、受験校をランクダウンさせるのは非常にもったいないです。それに、入試本番
まで、まだ4ヶ月もあるのですから。
毎年受験生に言いますが、「今、受験校をランクダウンさせるのは簡単。気持ちも楽。だけど、中学校ではみんな同じ
内容を勉強しているから、分かってくれないかもしれないけど、正直、高校というのは、高校によって、勉強している内容の
レベルが全然違う。高校受験のときにランクダウンさせると、大学入試に向けて勉強するときに、今よりももっと大変にな
る。問題を先送りしてるだけだよ。だから、あきらめてはいけないし、もっと上を目指して欲しい。」 と。
きちんと指示通りに勉強してれば、まだ伸びますよ。夢をあきらめてはいけません・・・。
差を知る
2014年11月05日
医学部・薬学部、容易く合格できる学部ではありません。これは皆分かってることです。でも、そこを志望するなら、
自らの実力と、ライバルとの実力差を知っておかなければなりません。
具体的には、校外模試の偏差値で知ることもできますし、合格判定で知ることもできます。そこで、十分、差を実感できる
はずですが、それを縮めようと努力することは必要だと思うのです。問題が「難しい」のは当たり前です。競争しているわけ
ですから。普通の問題なら、差はつかないのです。ですから、差が付くように難しくなる。それを解けるように、勉強しなけ
ればなりません。
大都市圏の中高一貫校は先取りで授業を進めていますが、それはそうした問題を解くための時間を確保するためでも
あるのです。でも、そうではない地方の高校生はどうするのか? 入試問題に対応すべく勉強するしかありません。正直、
時間が足りないのです。
高3が近づいてからどうこうしようというのではなく、高校に入ったらすぐに、いや、中学校の段階から、それは考えてお
くべきことだと思います。差は歴然としてあります。以前も書きましたが、大多数の高校で受験している校外模試には、
強豪の中高一貫校の生徒は、受験していないことも多いのです。受験当日になって初めて姿を現すライバルです。
高松高校生、高松一高生、通学に時間がかかるなか、よく頑張っていると思います。部活も皆頑張ってますしね。
三木高校生、定期テストも近づき、勉強のスイッチは入りましたね。でも、時間はもっと作れるはずですよ。時間があり
余って、逆に無駄にしていませんか?