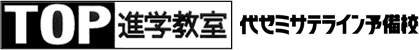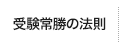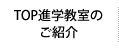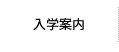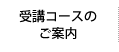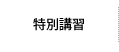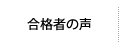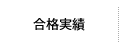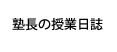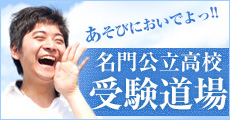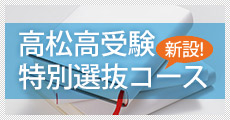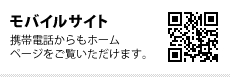【重要】8月30日(金)は、休塾
2024年08月29日
台風接近に伴い、8月30日(金)は「休塾」です。
自習室利用もできません。
模試も実施日時を延期します。
塾生の方は、メールおよびアプリにご連絡していますので、そちらもご確認ください。
模試は受けた方が良い
2024年08月28日
TOP進学教室では、小中高ともに、全国レベルの模試を受験しています。
それは、全国の同じ学年の受験者の中で、自分がどれくらいの位置にいるのかを認識してもらう、という目的があるからです。
中学校内で1位であったとしても、全国レベルで競争したら、いったいどのくらいの成績なのかというのは、やはり全国レベルの模試を受験しないと分かりません。これは、小中高ともに同じ。
小学校のテストで100点、中学校で1桁順位、高校の校内模試で1桁順位、といったところで、それと同等の成績をとっている同じ学年のライバルは、何千人、いや何万人、といることでしょう。それに気づいてもらうための模試受験です。
公立高校受験は県内受験生だから、県内の受験生のみが受験する模試で十分では? との考えもあるかとは思いますが、公立高校受験が最終目標ではありません。その後の、全国の受験生がライバルとなる大学受験を見据えれば、県内の順位で満足しているようではいけないと考えています。
ということで、塾生は、模試は全員受験ということになっています。
知らないことは、調べる
2024年08月26日
塾生が質問に来た時に、考えても分からない問題は教えます。もちろん、塾生の理解状況によって、どこまで教えるかは変えています。ちょっと説明すれば分かりそうな場合には、そこでストップしてその先はまず自分で考えるように促しますし、自力で考えるのが難しい場合には、最後まで説明します。
ですが、英語なら単語の意味が分からない、国語でことわざの意味が分からない、数学で用語の定義が分からない、歴史で人物のしたことが分からない、といったようなことがある場合には、まず塾生自身に「調べさせます」。それは調べれば分かることであって、質問に来る前にまず自分ですべきことだからです。
再々そういう指示を受けると、自分でまず調べる習慣がついて、そして、その段階で質問する必要がなくなることも多々あります。そうした質問が出てくるのは、「分からない」からではなく、「知らない」からです。「知らない」ことは、いくら自分で考えても出てきません。それは、「調べる」ことで解決します。
もちろん、私が、その「知らない」ことを懇切丁寧に教えれば、質問は解決するとは思いますが、その塾生の為にはなりません。ですので、教えたい気持ちを抑えて、「まずは自分で調べるように」と指示を出しています。
高松高・一高・三木(文理)合格のための「個別相談会」開催
2024年08月23日
高松高・一高・三木(文理)合格のための「個別相談会」開催中
「塾の授業では、どのように個別に指導するの?」
「志望校に合格するには、内申点や診断テストで何点必要なの?」
「合格するには何をどのように勉強すればいいの?」
そうした知りたいことを、まずはご相談してみませんか?
★ 事前予約制でお願いしております。日程につきましては、ご相談させていただきます。
★ 相談会参加は無料です。お問い合わせ、お申し込みは、こちらから
「高校で教えてもらってません・・・」
2024年08月22日
高校生の学習のメインは、まず、高校で学習した内容の完全理解であると考えています。
教科書、指定問題集、参考書を、高校の授業に沿って予習復習すれば、そんなに困ることはないですし、定期テストもラクラク突破できるはずです。
まあ、定期テストレベルは、そのくらいの学習でいいのですが、それを超えるレベル、つまり、模試や入試に出るレベル、になると、それ+αの学習が必要になってきます。
そうしたレベルの問題にぶち当たると、
「高校で教えてもらってません・・・」
と、質問に来る塾生もたまにいます。
確かに、その問題の解法は教えてもらっていないのかもしれませんが、既習内容ですから、まずは、自分の力で、教科書や参考書を調べたり、考えたりすることが必要です。高校の授業では、中学校の時みたいに、すべてを丁寧に教えてくれる訳ではありません。時間的な制約もありますし。
ですから、「教えてくれるまで待つ」のではなく、「自分で勉強する」取り組みが重要です。
TOP進学教室では、中学生の時から「個別演習型指導」を採り入れていて、自分で考えることを重視しています。「丁寧に教えてもらう」ことは楽ですが、その楽な分だけ、自分で考える力は弱くなります。「個別演習型指導」を長く経験しているほど、高校生になってからの、成績の伸長度が大きくなります。最近では、京都大学、大阪大学、広島大学、医学部等に合格した塾生は、中1から通塾していました(中には、小学校からの通塾生もいます)。
積極的に自ら勉強する習慣を身に付けるには、早い方がいいのです。
解けて当たり前の問題を100%確実に正解する
2024年08月21日
高得点を維持するには、応用問題を解けるようにすることも重要ですが、もっと重要なのは、
「解けて当たり前の問題を、100%確実に正解する」
ことです。
高校入試で、高松高校や高松一高を目指す場合には、他の受験生も各教科40点以上は取ってくるわけですから、ミスは致命傷になりかねません。誰もが解ける問題を、自分だけミスすれば、確実に差が開きます。授業中によく言いますが、誰もが解ける問題を確実に正解すれば、負けることはない、と。
解けて当たり前の問題を確実に正解することは、絶対に必要です。
そういう問題をミスするのは、やはり油断だと思います。解けて当たり前レベルだから、解く際にも注意力が散漫になりがちですし、見直しも十分にできていない可能性があります。易しい問題こそ、手を抜かずに解くべきです。
「国語読解解法の奥義」受講者の感想②
2024年08月20日
昨日に引き続き、「国語読解解法の奥義」受講者の感想の一部を紹介します。
なお、奥義に該当する部分は・・・で省略しています
・「今までテストで文章問題と向き合ってもどこをどう探すとよいかが分かっていなかったので、正直適当に書いていた部分もあったけれど、この授業で解き方が分かったので、テストに活かしていきたいと思いました。『診断テスト』は見たことのない問題が出るけれど、原則を覚えておけば、スラスラ解けるのではないかと思いました。」
・「今まで具体的な国語の授業をしたことがなかったので、知らなかったことをたくさん知ることができました。記述では・・・・・・・が一番役に立つと思いました。そして、気持ちを聞かれた場合には、・・・・・・・・・・・と答えればよいことが分かりました。」
・「いろいろなルールを知ったことは良かったです。いろいろなルールを知ったうえで、良いなと思ったのは『記述』です。特に、「記述』は国語の問題を見ると、とばしてしまうことが多くて、この授業で一歩成長することができた気がします。」
・「思っていたより短く感じた。授業を受けた後では、以前よりも問題が解きやすい感じがした。・・・・・を意識して解くようにしたい。自分の・・・・・・・ように解くことを意識したい。」
授業では、記述問題の解法を教え、記述問題にもチャレンジしてもらいましたが、苦手とする中学生が多いと思われる『記述』問題を、全員が書けました。もちろん、全員の解答が模範解答というわけではありませんが、それに近い解答を書けていました。
お盆明けから、講義で指導した解法が実際に使えているかを個別授業で確認していますが、解法を意識して解けています。いろいろな問題にチャレンジしてもらい、解答の精度を上げていきます。
「国語読解解法の奥義」受講者の感想①
2024年08月19日
中学生対象の「国語読解解法の奥義」受講者の感想の一部を紹介します。
なお、奥義に該当する部分は・・・で省略しています
・ 「国語の文章を読むときのコツを今日学んで、自分は今まで読むのが非効率的だったと思いました。例えば、指示語の内容を探すときに、かなり前の方から読み返していましたが、・・・・・に答があるのだと学びました。このような新しい発見が今日はたくさんありました。新しい発見ということは、今まではできていなかったということなので、今日学んだことを使って、問題を効率よく理解し、素早く解けるようにします。」
・「今まで僕は4時間も続けて国語の勉強をしたことは一度もありませんでしたが、今回教えてもらえたことはとても役に立ちそうでした。想像していた複雑なルールとは違い、・・・・・ただそれだけのルールで、覚えるのも非常に簡単そうでした。いつも国語に対して抱いていたとても大きな嫌悪感が少し小さくなったように感じました。けっこうズバっと書いてくれたので、迷いなく理解することができました。」
・「もっと早く今日学んだことを知りたかった。4時間も苦手な国語の勉強をするのは嫌だったけど、意外にすぐに終わった。少し楽しかった。めっちゃ賢くなった気分になった。」
・「国語の大原則が、自分の思う大原則と全く違って驚いた。・・・・の問題は、・・・・・・を使ってみると、これまでの自分が何だったのかと思うほどに簡単に解けるように感じた。」
・「初めは『4時間もできるかな?』と思っていたけれど、意外と早く時間が進み集中できた。今まで記述問題を書くとき、たまに・・・・・・・・・・・・けど、・・・・だけで簡単に解くことができた。今まで書き抜きで・・・・・・・が、1回で見つけることができた。」
②へ続きます。
「夏期講習」終了
2024年08月09日
TOP進学教室の「夏期講習」は、本日で終了しました。
一部コースは、お盆明けも継続して、「夏期講習」内容の指導を継続します。
お盆明けからは、「8月度」の授業があります。
高校生は、8月末の「校内実力テスト」に向けて、また、中学生は9月の「中間テスト」に向けて指導していきます。もちろん、中3生は9月初旬の「診断テスト」対策も継続して指導します。
明日10日(土)は、中学生対象の「国語読解解法の奥義」の授業があります。今年も満席です。
世の中が「お盆休み」モードに入りつつありますが、中3、高3受験生は、それに完全に流されてしまってはいけません。「お盆休み」をしなければならないわけでもないですし、「お盆休み」なく働いている方もたくさんいます。ちょっと勉強の手を緩めたいから、自分で勝手に「お盆休み」モードにしたい気持ちは分からなくもないですが、見えないライバルは全国にたくさんいます。
受験までの日数(入試日)が決まっているのですから、ライバルよりも先行して取り組む必要はあります。
受験生の皆さんは、オリンピック、お盆休みに流されることなく、継続して取り組んで欲しいです。
とはいえ、家族の行事(お墓参りとか旅行とか親族訪問とか)がある場合には、参加した方がいいですね。家族の対話も増えますし、リフレッシュもできますので。
お盆明け以降の「8月度」授業からの受講生も募集しています。コースにより、満席の場合もありますので、まずはお問い合わせください。こちらから
教えてもらうだけでは伸びない
2024年08月08日
「成績が良くなかったから塾へ」
そういうきっかけで通塾する人も多いはずです。
ですが、「なぜ成績が良くなかった」のか、原因は考えたでしょうか?
私が思うに、一番の原因は、
「勉強不足」です。
「勉強したけど、思うように成績が伸びなかった」という場合もあると思いますが、それは勉強の中身がよくなかったことが多く、勉強のやり方、内容を変えれば、改善することも多いです。
ですが、「勉強不足」は、そもそも勉強時間が不足しているのですから、勉強の中身も重要でしょうけど、「勉強時間」の確保が必要です。
TOP進学教室の高校部は、一斉授業は行っていません。個々の状況に応じて、指導する内容は変えて、指示をしています。
高校の課題が思うように進められていないから成績が低迷している場合には、その課題を重点的に取り組む指導を、
指定された教材を家庭学習で取り組めていない場合には、自力で取り組めるようまずは塾の授業時間内で、その教材を用いた指導を、
学校教材を自力で終えることができている場合には、それ+αの教材を、
家でなかなか取り組めない場合には、自習室での学習を支援する指導を、・・・
個々に変えて指導しています。
そうした指導で、「勉強不足」は多少改善されるかもしれませんが、塾で勉強できる時間は、しれています。やはり、家庭でどれだけ取り組めるかにかかっています。家庭で出来ないのであれば、自習室等で勉強するのでも構いませんが、そうした自ら取り組む勉強をしなければ、伸びることはないでしょう。
いわゆる、「自学力」というのは、必要になってきます。
塾で教えてもらう内容が増えれば増えるほど、家庭学習の時間も増やさなければなりません。塾で教えてもらってるから大丈夫、って考える高校生もいるかもしれませんが、それは間違いです。